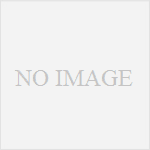おかげさまでこの連載も20回目を迎えることができました。いつもご覧いただき、ありがとうございます。
当初イメージしていたよりも、運賃やタリフに関する話題が少なめで、むしろ路線とか経済状況とか周辺の話題が豊富な内容になっていますが、今回は「キャリア運賃がどうやって浸透していったか」のひとつの例として、「運賃名称」に着目してお話したいと思います。
※ 前回の予告で、アライアンス運賃について触れるつもりでしたが、よく考えたら「それはもう少し先だな」と思い直したので、変更しています。
キャリア運賃の「名称」とは
そもそも今回のテーマの前提として、「なぜキャリア運賃に名前を付ける必要があるのか?」というところから始めます。
旅行あるいは航空業界で働いていると、「キャリア運賃」とか「IT運賃」という呼び方が、ごく当たり前のもののように感じられます。しかし、一般の旅行者にしてみれば、どんな運賃だろうが、同じ座席やサービスで、同じ目的地に運ばれるのですから、特に区別はありません。もちろんビジネスクラスとエコノミークラスでは運賃体系が全く異なるのは当然として、同じエコノミークラスであれば、高いものと安いものがある、程度の認識でしかないわけです。
そこに「これはITですね」とか「これはIATA運賃だから高いですよ」と言っても、買う方はよくわかりません。IATA運賃なら他の航空会社にも乗れると言われたところで、直行便で一気に飛ぶつもりだったら不要な知識ですし。
ほとんどの旅行者は「安い運賃=格安航空券」と捉えていたでしょう。ITばら売りですね。「キャリアが独自に設定して直販しているPEXです」と言って新しい商品を売ろうとしたところで、「それ、格安航空券じゃないの? どう違うの?」と聞かれるわけですから、だったら一目でわかる覚えやすい名前をつけて、キャリア運賃を認識してもらおう、と考えるのは自然なことではないでしょうか。
今日では、キャリア運賃が一般的になり、むしろIT運賃、いわゆる格安航空券の方が珍しいような状況になってきましたから、各航空会社とも、いちいち運賃名称を考えて設定していません。少し寂しい感じもします。
運賃名称の例
OFCは(忘れられがちですが)JALグループですので、日本航空のキャリア運賃の名称を見てみましょう。
現在、普通運賃よりも安いキャリア運賃は「セーバー」。その中でも特に安価な期間限定などのものは「スペシャルセーバー」と名付けられていて、他の航空会社とさほど変わりません。あんまりおもしろくないですね。
タリフ書籍を1994年4月版まで遡って見ると、出てきました「JAL悟空」です。
業界に長くいらっしゃる方であれば、この名前をご記憶のことでしょう。ぼくが覚えている限り、自分が大学生だった2000年代半ば、IT運賃に対抗してJAL悟空を積極的に売るべく、いろんなところに広告が出ていたような。たしか、格安航空券との差別化を図るポイントとして「マイルが貯まりやすい(積算率が高い)」「購入時点で便が確定する」「座席指定もできる」なんてことが挙げられていた気がします。
それはともかく、「JALと言えば悟空」と覚えてしまえば、実にわかりやすい名称。
この運賃名称、GDSには登録がなく、各航空会社が営業用につけたものです。OFCタリフシリーズには「名称」としてそれぞれ載っていますので、一度ご覧になってみてください。
同じ94年4月の本で、他の航空会社を見てみましょう。けっこう懐かしい会社が出てきますよ。
AA(アメリカン航空)「スーパー個人運賃」
なんか普通と言うか地味な名前ですね。団体向けのITに対して、個人旅客はこちら、という趣旨でしょうか。
CS(コンチネンタルミクロネシア航空)「バジェット エクスカーション運賃」
ホノルル行きの設定だけという事情もあるのかどうか、出張ではなく休暇でどうぞ、という雰囲気が出ています。
NH(全日本空輸)「とび丸運賃」
こんな名前でしたっけ?
UA(ユナイテッド航空)「フレンドリー PEX運賃」
家計に優しいユナイテッド航空、ということではないでしょうが、設定都市が多いのが魅力。西海岸からフロリダ半島まで広範囲にカバーしていて、便利そう。
IW(AOMフランス航空)「AOMペックス運賃」
社名を入れるのが、ひとつのスタンダードでしょうか。
KL(KLMオランダ航空)「フラワー ペックス運賃」
チューリップで知られるオランダは花の国。というわけで、その国を代表する航空会社は、直感的にどこの国かわかるものを使う、ということもあるんですね。
CX(キャセイパシフィック航空)「キャセイ マジック運賃」
どこに連れて行かれるんでしょうか。
TG(タイ国際航空)「サワディー運賃」
どうもこんにちわー。
それでは次回、この時期のキャリア運賃がどういう設定になっていたのか、航空会社別に運賃表などを見比べてみたいと思います。
この記事を書いた人:
関本(編集長)