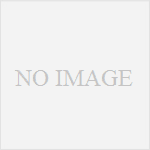前回、全日本空輸の1990年代の運賃表を見ました。どうでしょう、今と比べて意外に高いと感じましたか。あるいは、ゾーンPEXでも案外安かったんだな、という感想を持たれたでしょうか。
これまで、運賃を時期ごとずいぶん細切れに見てきましたので、今回は全体としての流れを振り返ってみたいと思います。
最近の運賃の傾向
新型コロナウイルスの影響を受けて、国際線は大減便を余儀なくされ、ちょっと前まで日本発着国際線はほとんど死んだような状態でした。
1年ほど前でしょうか、国内線に乗るのに成田空港から出発する機会があり、第2ターミナルの国際線出発ロビーを覗いてみたところ、全然人がいません。チェックインカウンターも電気を落としてひっそりとしているところが多く、いつもの賑わいを知る身としては、大変悲しい思いをしました。
さて、需要がなく、供給もないとなると、運賃はどうなるのか。
前回まで、主に70年代から90年代にかけて、航空運賃が下がってくる歴史を見てきましたが、これはジャンボジェットによる供給増に対し、なんとか需要を喚起して座席を埋めたいという思惑が初期にあり、その後、実態とかけ離れた旅行会社経由の運賃に呼応するように、キャリア運賃も値下がりしていった、というのが大まかなところでした。
しかし、突然需要も供給も消えてしまうと、まず安売りして座席を埋める理由がなくなりますね。乗る方だって、「こんなに安いんだった行ってみよう」とはならないわけです。
2020年から21年までの各航空会社の運賃を振り返ってみると、普通運賃に近い片道の設定がわりとありました。これは出張や観光需要を想定したものではなく、赴任や完全な帰国に使われることを意図しているようで、高くても乗らなきゃいけない人が買いますから、安売りはありません。
よって、過去と現在の運賃を比較するのに、便宜的に2019年までのものを参照してみます。
2019年に見かけた安い運賃
以前、このニュースレターでも少し触れましたが、OFCでは年に何度か、大学で国際航空運賃に関する講義を行っています。今年もそれがあったので、次号くらいでご紹介したいと考えています。
その講義で使う資料の中に、現代はいかに安い運賃が出回っているかという説がありまして、そこで取り上げているのはベトナム航空のヨーロッパ行き。燃油サーチャージや諸税は別にして、2019年の冬、ロンドンとフランクフルトまで往復いくらだったと思いますか?
答えはなんと「2万円」。ハノイまたはホーチミンシティで乗り換えなければならず、飛行時間も長いため、決して人気の航空券ではないんでしょうが、それにしても安い。安過ぎます。
興味は引かれたものの、残念ながら、この運賃でヨーロッパに行く機会はありませんでした。
ちなみに、ぼくの中でヨーロッパ行きの最安値は、2016年のカタール航空。イタリア往復5万円台(総額。カタール航空は燃油サーチャージがなく、その点でもお得)でした。片道20時間くらいかかりますが、値段を考えると、つい選んじゃいますね。
それはともかく、10万円でお釣りがくるレベルで、今は(世の中が正常なら)掘り出し物を見つけてヨーロッパに行けるんだ、ということです。
昔の運賃を振り返る
この連載の10回目で、OFCが生まれた1984年のタリフを紹介し、ロンドン行きの運賃を載せていました。
これによると、エコノミークラスで405,400円(片道)。今も普通運賃は同じくらいでしょうか。ただ、当時はこれより安い運賃の入手経路が限られていた、というのがポイントですね。物価の変動を無視しても、2010年代後半には、航空会社から直接買える運賃が、10分の1かそれ以下まで下落していたようだ、というのがわかります。
ちなみに、この記事では国家公務員の初任給を基に物価上昇率を計算していて、1984年(昭和59年)と2019年(平成31年)では、初任給は約1.66倍になっていました。と考えると、ロンドン往復が今の価値で130万円を超えてくるわけで、ベトナム航空で行けば昔の15分の1の値段でヨーロッパまで辿り着けちゃったわけですね。
なぜ今回、こんな話をしたのかと言うと、航空需要の回復が早いアメリカとヨーロッパでは、コロナ禍以前よりも運賃相場が上昇しているという文章を見かけたから。
まだぼくも分析中でして、実際どうなんだ、というところまでは行きつけていません。
日本に目を転じると、国際線は供給がやっと増えてきた段階で、ごく限られた人しかまだまだ海外に行かないですから、相場を読むのは難しい。ただ、インバウンドがないために、国内線は需要を喚起する目的でタイムセールが連発されています。日本航空も全日本空輸も、気がつくとセールやってるな、と感じます。
実際、国内線に乗ってみると、驚くほど乗客が少ない便もあり、アメリカ、ヨーロッパとは異なる動きが続きそうです。その中で、運賃に関して新しい動きがあれば、発信していきたいと考えています。
それでは、また次回。
この記事を書いた人:
関本(編集長)