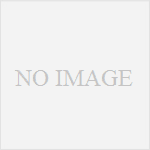前回は物価統計を参照しながら、航空運賃の変動を見てきました。
その終わりに2019年以降、コロナ禍を経て国際線の供給座席数が絞られたのではないかという話をしましたが、その辺、国土交通省が報道発表を出していましたので、そんなところを今回は学んでみたいと思います。
国際線旅客数の推移
今回参考にするのは、国土交通省ウェブサイトの「我が国の航空輸送の動向」という節。まずは以下のリンクをご覧ください。
2ページ目が国際線についてです。
これは日本人出国者と外国人入国者をまとめてひとつの表にしていますが、世界経済等の影響で瞬間的に落ち込む年を除き、一貫して右肩上がりでした。それが令和2(2020)年に向けて急落し、限りなくゼロに近い数になっているのがわかります(2020年は春節くらいまで外国人観光客の入国も多かったので、いきなりゼロではありませんが)。
就航便数の動向
上記リンクは、このページでまとめられているものです。
航空輸送の現状(国土交通省ウェブサイト)
これの中段、「各期の国際定期航空便の主な動向」に、半年ごとの国際線の動きがまとめられています。
ちなみに、なぜ半年ごとなのかと言うと、各航空会社は毎年2回、夏と冬のスケジュールの切り替えに合わせて、国土交通省にスケジュールを申請し、認可を受けます。この情報を基に集計しているので、夏期スケジュールと下期スケジュールになっているわけです。
なお、OFCでは各航空会社のスケジュール申請のお手伝いもしております。自社ではなかなか手が回らないとお困りのご担当者様、ぜひOFC担当へお問い合わせください。
さて、週次の国別就航便数を抜き出して、19年度と22年度を比較してみました。
※ 就航先ではなく、航空会社の所属国での集計です。また、全体的な動向を掴む意味で、貨物便も含めてみました。
| 19年夏 | 22年夏 | 19年比 | |
| 日本 | 1,503.5 | 736 | 49.0% |
| 韓国 | 1,209.5 | 87 | 7.2% |
| 中国 | 896 | 74.5 | 8.3% |
| その他アジア | 1,496.5 | 315 | 21.0% |
| 米国 | 462.5 | 324 | 70.1% |
| 欧州 | 236 | 66.5 | 28.2% |
| その他 | 149 | 57 | 38.3% |
前提として、19年夏スケジュールは、就航便数が過去最高を記録し、インバウンドも好調、アウトバウンドもまぁまぁ円高基調で少なくなかった時期です(冬の方が若干減るので、そこからコロナ禍に突入し、未だ完全回復せず)。
本邦社、つまりANAやJALですが、22年は業務渡航や外国を日本経由で繋ぐ需要に支えられて、概ね半分程度回復。スケジュール申請時点ということは、まだ日本の入国規制がかなり強かった時期でもあり、それにしてはずいぶん飛ばしているな、という印象かもしれません(ただし、機材をダウンサイジングしていれば、供給座席数はもっと少ない。特に2022年時点では長距離国際線の主力機であるボーイング777型機が運航停止になった影響もあり、各社平均して若干小さめの機体に移行している可能性はあります)。
圧倒的回復は米系ですね。70%の便が復活しています。実際、アメリカの大手航空会社のウェブサイトを検索すると、便の選択肢は豊富。いち早く国内線から復便し、マスク着用義務を撤廃し(賛否両論あるでしょうし、そうすべきという話ではありません)、業績が急激に回復してきているのが、こんなところからも読み取れます。
一方で、落ち込みが続くのは韓国と中国。
韓国は19年がとにかく多かったという事情もあって、この年の冬スケジュールでは政治的な問題で急ブレーキがかかった(でもそれなりに供給はあった)ところからも、一種のバブルという感じがします。そこから比べると、まだ1桁台というのは仕方ないでしょう。
また、中国はゼロコロナ政策が継続し、国際線利用客の絶対数が少ない。政府が就航便数をかなり制限している、ということで復活ならず。
ここには載せていませんが、22年冬スケジュールで韓国社は、夏の約6倍となる485.5便/週の運航を予定しています。観光客の入国に際してビザの要件を撤廃し、日本人が行きやすくなった韓国。こうやって往来は戻ってくるのだな、ということを実感します。
対して中国は、便数は約1.5倍に増えるものの、未だ19年対比で10%という低調ぶり。中国の場合、春節の移動を睨んで下期の方が便数が多いという元々の傾向もあるのかもしれません。それで考えると、単純に訪日観光客が多かった(秋葉原も銀座も、どこに行っても中国人観光客だらけで、すごい賑わいでした。なんかもう懐かしい)19年度と比べるのは、些か分が悪いとも言えるでしょう。
もっと精緻に、運航されている便数を運賃額の変化と対照させてみると、またおもしろかったりするのですが、このコラムのテーマから反れますので、この辺で。
それでは、また次回。
この記事を書いた人:
関本(編集長)